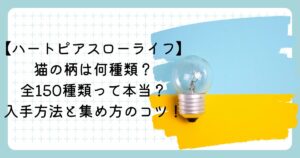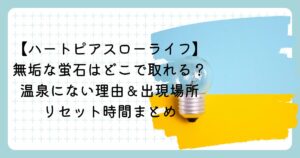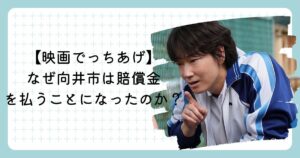片山慎三監督の長編デビュー作にして、その圧倒的なリアリティと衝撃的な内容で口コミが広がった映画『岬の兄弟』。
「実話ではないか?」と錯覚するほどの生々しい質感、ドキュメンタリーのようなカメラワーク。
そして何より、観る者の倫理観を揺さぶるあの「ラストシーン」について、今もなお多くの議論が交わされています。
今回は、
映画「岬の兄妹」最後の電話シーンは誰からだったのか
について調査していきます。
【あらすじ】映画「岬の兄妹」が話題

そもそも「岬の兄妹」とはどのような映画なのでしょうか。
舞台はどこにでもありそうな地方の港町。
仕事をクビになった兄・良夫(小児麻痺の後遺症あり)と、知的障がいを持つ妹・真理子。
貧困のどん底にあえぐ二人が選んだのは、妹の身体を売るおしごと)でした。
ドラマチックな起承転結ではなく、日本のどこかに確かに存在するかもしれない底辺の日常が、淡々と、しかし残酷に描かれています。
考察「岬の兄妹」最後の電話シーンは誰からだったのか
兄・良夫が真っ当に生きようと決意し、仕事に復帰しようとした矢先のラストシーン。
崖(岬)に佇む真理子を見つめる良夫の携帯電話が鳴り響きます。
あの電話は一体何だったのか?
そして、なぜ良夫はあのような表情を見せたのでしょうか?
考えられる4つの有力な説を見ていきましょう。
「岬の兄妹」最後の電話シーンは誰からだったのか考察①:警察から妹が見つかったという知らせ
一つ目は、最も悲劇的な解釈です。
直前に良夫は、警官の肇(ハジメ)くんに「妹が見つかったら電話をくれ」と頼んでいました。
ですので電話の内容は、警察からの「妹(の遺体)が見つかった」という知らせなのではないかと考察されています。
そして実は良夫が見ている岬の真理子は、彼の罪悪感や未練が見せている幻覚だったとも言われています。
兄が電話に出る瞬間に震えたのは、これから対面しなければならない残酷な現実への恐怖だったのかもしれません。
「岬の兄妹」最後の電話シーンは誰からだったのか考察②:客が来た合図
「たとえ生きていたとしても、もう昔の二人には戻れない」という、精神的な終わりを描いた説です。
•電話の着信音が鳴った瞬間、真理子の表情がパッと変わったことから、 真理子にとって着信音は、すでに「客が来た合図=おしごとの時間」として脳に刻まれてしまっていると考えられます。
まっとうな職に就き、やり直そうとしていた良夫ですが、電話一本でおしごとの道具の顔に戻ってしまう妹を見て、自分たちが犯した罪は、一生消えないと悟った絶望の瞬間と言えます。
「岬の兄妹」最後の電話シーンは誰からだったのか考察③:貧困からは逃げられない再開の合図
一度踏み外した道からは、そう簡単に戻れないという社会の厳しさを示す説です。
電話の主は警察ではなく、かつての客や依頼主。
真面目に働こうとしたものの、一度でも楽に大金を得る快感を知った人間は、過酷な底辺生活には耐えられません。
結局、鳴り止まない電話に慌てて出る良夫の姿は、再び妹を売る生活へと戻っていく未来を暗示しています。
人間、少しでもいい暮らしをしてしまうと、もう元の大変な生活には戻れないというような貧困の連鎖を象徴していると考えられます。
映画「岬の兄妹」は実話?元ネタやモデルはある?
2019年に公開され、日本映画界に激震を走らせた映画「岬の兄弟」。
衝撃的なテーマの映画ですが、ネット上では「これって実話なの?」と疑問の声が上がっています。
結論から申し上げますと、
映画「岬の兄妹」は完全なフィクションであり、特定のモデルとなった実話(事件)は存在しません。
漁村や闇市を彷彿とさせる荒廃したエリアで、その日暮らしを続ける兄妹。

「岬の兄妹」は実話ではありませんが、日本のどこかで、今この瞬間も起きているかもしれないことを突きつけてくるような作品です。